| Q 定義 (2) |
| Q>0 を渦領域とするのが Q 定義である。 図8 は、Q の等値面をしきい値の大きいところから徐々に 小さくしていって、渦軸と比較したアニメーションである。 Q の等値面は全て、ほぼ管状構造を保ちながら、少しずつ太くなっていき、 また、その数も増加していく様子が観察される。 これに対し、圧力の等値面は早い段階で等値面が 大きなかたまりとなってしまい(図5)、また、エンストロフィー密度の等値面 では、管状渦構造ばかりでなく層状構造も同時に現れてくる(図6)。 従って、旋回運動を伴う管状渦構造を抽出するためには、しきい値を大きく 選んだ Q (あるいは圧力のラプラシアン)の等値面が、圧力や エンストロフィー密度の等値面に比べてより適切であるといえる。ところで、しきい値をゼロととるのがもともとの Q 定義であったが、 このとき、等値面は空間の 40% 程度も覆ってしまうため、 渦構造の特定という本来の使命を失ってしまうことに注意する。 | 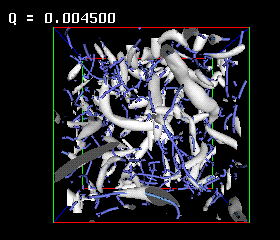 |
ここで、圧力断面極小法と Q 定義を比較してみる。 圧力断面極小法は圧力のヘシアンの固有値を用いて、 渦領域の条件を λ(1) ≧ λ(2)> 0 としている(式 (2))。 ところが、 λ(1) +λ(2) + λ(3) =∇2p =2Qなる関係があるので、この断面極小条件が成り立つと、 自然に Q > 0となる傾向にあり、 逆に、大きな Q に対しては、 λ(2)> 0 である確率が高くなる。 この意味で、両者はよく似た条件であるといえる。 しかし、たとえ Q > 0 であっても λ(2)< 0 である可能性は常に存在する ので、両者は同等ではないことは明らかである。 幾何学的には、圧力断面極小条件は、 第3固有ベクトル ( ε3 ) に垂直な平面で圧力が極小になることを意味する。 これに対して、Q > 0は、3つの直交する方向への曲率の和が正であることを 述べているが、これは圧力分布の極小条件とは対応しない。